「朝は1分も余裕ない!」→コーヒーの待ち時間に冷蔵庫の取手だけ拭く習慣、やってみた

「朝は1分も余裕ない…」そう感じるのは、あなただけではありません。
目覚ましを止めた瞬間から脳内はフル稼働。メイク、着替え、朝ごはん、子どもの支度…ひとつタスクが遅れるだけで、すべてがグダグダになる。だからといって「掃除」まで手が回らないのは当然です。
でも、そんなギチギチの朝にも“スキマ”はあるんです。
たとえば、コーヒーを淹れるあの数分間。実は、この「待ち時間」に1つだけ家事を差し込むことで、心の余裕がグッと生まれます。
私が実践しているのは、「冷蔵庫の取手だけ拭く」習慣。
えっ、それだけ?と思った方、ぜひ試してみてください。
ポイントは、“小さな範囲”かつ“毎日触れる場所”を選ぶこと。冷蔵庫の取手は、キッチンの中でも特に汚れが溜まりやすい場所です。でも面積は小さいから、1分で十分拭ける。やり切れる。終わったあとの「やった感」が意外とクセになります。
こうした“待ち時間家事”は、マイクロハビット(小さな習慣)の典型例。
毎日ほんの1アクションでも積み重なると、生活全体に「ちゃんとしてる感」が染みわたっていきます。
「何かしたいけど、何もできてない自分が嫌」──そんな思いを手放す一歩として、まずはこの“冷蔵庫の取手1分掃除”、始めてみませんか?
関連記事
忙しい朝でも「整った暮らし」は作れる
「朝、家を出るだけで精一杯なのに、“整った暮らし”なんて理想論でしょ?」そう思う方も少なくないでしょう。でも、暮らしの整い方って、実は“丁寧さ”ではなく、“繰り返し”で生まれるものなんです。
整っている家の秘密は、完璧な家事ではなく、小さな習慣の積み重ね。
毎日少しずつ、同じ行動をくり返すことで、自然と生活に“整い”が染み込んでくる。朝のスキマ時間を利用した「冷蔵庫の取手を拭く」ルーティンも、まさにその代表格です。
家事って、「やるぞ!」と思って始めると、逆に腰が重くなるもの。でも、「コーヒーの待ち時間に取手だけ拭く」なら、ついで感覚で手が伸びやすい。
この“ついで行動”が続くと、気づかぬうちに「毎日何かやれてる自分」に変わっていくんです。
ここで得られるのは、“整った家”そのものだけじゃありません。
「今朝もちゃんとできた」という達成感、自分を管理できているという自己肯定感。忙しい日々の中で、たった1分で手に入るこの感覚は、思っている以上に大きな価値があります。
だから、理想的な暮らしを目指すために、すべてを完璧にしようとしなくていい。
「1分でもできることがある」ことに気づくだけで、今の生活はグッと変わりますよ。
家事を「小分け」にすることの心理的効果
「掃除しなきゃ…でも時間がない!」このプレッシャー、あなたも感じたことありますよね?
実はこの“やらなきゃ感”こそが、家事に対するハードルを無意識に上げてしまう原因なんです。
そこで効果的なのが、“家事を小分けにする”という考え方。
大きなタスクをそのままやろうとすると、「よし、今日は冷蔵庫を丸ごと掃除しよう!」みたいな構えが必要になり、結局後回し。
でも、「今日は取手だけ」と範囲を絞れば、取りかかるハードルがグッと下がります。
このアプローチには心理的な裏付けもあります。
人間の脳は、ひとつのタスクを完了すると“ドーパミン”という達成感をもたらすホルモンを分泌します。
そして、このドーパミンが「次もやろう」というやる気に繋がっていくんです。
つまり、小さな家事をこまめに積み重ねることで、「もっとキレイにしたい」という好循環が生まれるんです。
これが、“暮らしを整えるスイッチ”になります。
「冷蔵庫の取手だけ」「シンクの蛇口だけ」「電子レンジの扉だけ」…そんな“小さな習慣”が、自己管理できている実感と、日常の満足度を確実に引き上げてくれます。
完璧じゃなくていい、むしろ“完璧を目指さない”から続く。それが「小分け家事」の魅力です。
「習慣化」の鍵はハードルの低さ
どんなに良い習慣でも、「続かなきゃ意味がない」──これは誰しも一度は思ったことがあるはず。
でも、そこで重要になるのが“ハードルの低さ”なんです。
「今日は時間があるから掃除しよう!」ではなく、「今日も時間がないけど、1分だけできることがある」。
このマインドセットこそが、習慣化を根づかせる鍵なんですね。
人間は、“脳のエネルギー消費”を本能的に避けようとする生き物。新しい行動を始めるときには必ず“抵抗”が生まれます。
だからこそ、始める行動は“極限までシンプルに、簡単に”するのがベスト。
「冷蔵庫の取手を拭く」という習慣のハードルの低さは、まさに理想的。
・1分で終わる
・道具は何でもOK(布巾、ティッシュ、アルコールスプレー)
・その場で完結(動き回らなくていい)
この3拍子がそろっているから、続く。続くから、生活が変わる。
さらに言えば、手を動かす“トリガー(きっかけ)”を明確にすることで、習慣化の成功率は格段にアップします。
今回のように「コーヒーを淹れたら拭く」といった“セット化”がその代表例。
これは「If-Thenプランニング」と呼ばれる心理テクニックで、「○○したら△△する」とルールを決めることで、脳が迷わず自動的に行動できるようになるんです。
つまり、“意思の力”に頼らず続けられる仕組みさえ作れば、誰でも習慣は身につきます。
毎朝1分の行動が整った暮らしをつくる
たった1分の行動なんて、意味があるの?──そう思う気持ち、よくわかります。
でも実は、その“たった1分”が、あなたの暮らし全体に与える影響は想像以上に大きいんです。
朝の時間は、一日の始まりをつくる“スイッチ”のようなもの。
そのスイッチが「ぐちゃぐちゃ」だと、心も頭も落ち着かず、ずっとバタバタのまま過ごすことに…。
逆に、朝に1つ「ちゃんとできた」と思える行動があるだけで、自分への信頼感がグッと高まります。
「冷蔵庫の取手を1分拭いた」──それだけのことが、「私は自分を管理できている」という実感に直結するんです。
小さなことでも“積み重ね”があると、生活の輪郭がくっきりしてくる。結果的に、部屋も、心も、どんどん整っていきます。
しかもこの習慣、家族にも伝染します。
取手がいつもキレイだと、他の人も「ちょっと気をつけよう」と思うようになり、キッチン全体の清潔感が自然に保たれるようになります。
「自己管理ができている」「暮らしをコントロールできている」──この感覚は、ただの掃除以上の価値があります。
そしてそれが、忙しさに流されない“自分の暮らし”をつくる土台になるんです。
まずは1分、冷蔵庫の取手を拭くところから。
それが、整った暮らしへの最初の一歩になりますよ。
やらないことで積もる“汚れ”と心のモヤモヤ
「たった1分のことだし、まあ今日はいいか」──そうやって1日、また1日とスキップしていくと、気づけば“なんかごちゃごちゃしてる家”が出来上がっていきます。
冷蔵庫の取手は、汚れてもすぐに生活に支障が出るわけじゃありません。
だからこそ、ついつい見て見ぬふりをしてしまう。そして、ある日ふと触ったときに「あれ?ヌメッとしてる…」そんな感覚にドキッとすることになります。
実はこれ、ただの汚れの問題だけじゃないんです。
「やろうと思っていたのにできなかった」という経験は、小さくても心に“自己否定”を積み上げていきます。
「私って、ちゃんとできない人なんだな…」と、無意識のうちに自分を責めてしまうんですね。
しかもそれが積もると、「掃除=めんどくさいもの」「もう手がつけられない」になってしまい、やがて“放置すること”が当たり前に。
これはまさに、汚れと自己嫌悪が同時に蓄積される負のループです。
だからこそ、逆転の発想が大切です。
「1分やるだけで、未来の自己嫌悪を防げる」と考えると、行動の意味がまるで違って見えてきませんか?
何もしなければ、現状維持ではなく“ゆるやかな悪化”が始まるのが生活のリアル。
だからこそ、今日から始める1分が、明日の自分を救ってくれるんです。
\ 今すぐチェック! /
🔹 おすすめ時短グッズまとめ(楽天ROOM)
👉 他の時短家事テクもチェック!
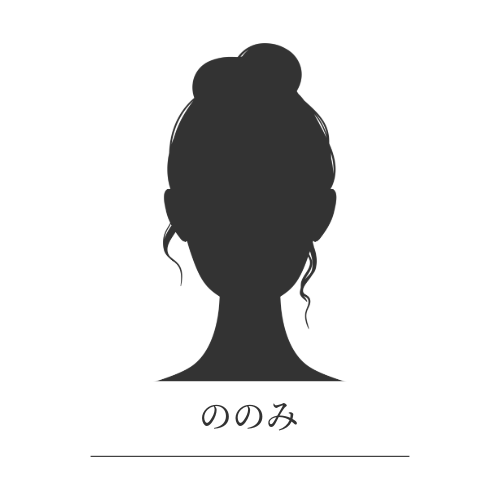
ズボラ主婦でもOK!家事を10分で終わらせる「時短家事ラボ」運営
家事の手間を半分に減らすアイデア発信!
掃除×時短
料理×ラク家電
育児×家事効率化
「時短家事テク」を学べるブログを書いています。



